ROI事件ファイル No.321|『NexBridge社の見えない目標』
📅 2025-11-16 23:00
🕒 読了時間: 22 分
🏷️ OKR

第一章:目標という幻想——やることリストが組織を止める
Frontier Booksのジョブ理論事件が解決した翌週、今度は東京から中堅IT企業の目標管理に関する相談が届いた。第二十七巻「再現性の追求」の開幕となる第321話は、バラバラの目標を一本の軸で繋ぎ直す物語である。
「探偵、我々の会社は急成長しています。従業員は3年前の48名から現在128名まで増えました。しかし、組織が大きくなるにつれて、各部署が別々の方向を向き始めました。営業は売上目標、開発は機能実装数、カスタマーサクセスは対応件数……。数字は達成しているのに、会社全体として前進している実感がありません」
NexBridge Solutions社 の経営企画室長、港区出身の橋本健太は困惑を隠せずにベイカー街221Bを訪れた。彼の手には、各部署の目標達成レポートと、それとは対照的に「方向性の不一致」と記された経営会議の議事録が握られていた。
「我々は東京で中小企業向けのSaaS型業務管理ツールを開発・提供しています。創業7年目。顧客数は1,200社まで成長しました。しかし、部署間の連携が取れません。営業が獲得した顧客を、開発が十分サポートできない。カスタマーサクセスが要望を集めても、開発の優先順位に入らない」
NexBridge社の目標分断: - 設立:2018年(SaaS型業務管理ツール) - 年間売上:18億円(前年比+42%) - 従業員数:128名(営業32名、開発48名、CS28名、管理20名) - 顧客数:1,200社 - 顧客満足度:68%(業界平均82%) - 解約率:月8%(業界平均4%) - 問題:各部署が独自の目標を持ち、会社の方向性が共有されていない
橋本の声には深い危機感があった。
「問題は、目標設定が『やることリスト』になっていることです。営業は『新規契約100社』、開発は『新機能20個実装』、CSは『月間問い合わせ対応500件』……。これらの目標を達成しても、顧客満足度は上がらず、解約率も下がりません。なぜなら、各部署が自分の仕事を終わらせることだけに集中しているからです」
典型的な部署間の分断:
営業部の目標達成:
営業部長: 「今月も目標の新規契約100社を達成しました! 素晴らしい成果です!」
経営陣: 「よくやった。では、なぜ解約率が8%もあるのか?」
営業部長: 「それはカスタマーサクセスの問題です。我々は契約を取ってきています」
開発部の言い分:
開発部長: 「今四半期も新機能20個を実装しました。計画通りです」
経営陣: 「しかし、顧客が最も要望している『レポート機能の改善』がまだ入っていない。なぜか?」
開発部長: 「それは優先順位が低かったからです。我々は実装数の目標を達成しています」
カスタマーサクセス部の悲鳴:
CS部長: 「顧客から『使いにくい』という声が月300件届いています。でも、開発部は対応してくれません。営業部は契約を取ってくるだけで、その後のフォローがありません。我々だけが板挟みです」
橋本は深くため息をついた。
「会議で各部署が報告します。『目標達成しました』と。でも、会社全体としては何も良くなっていません。顧客満足度は68%のまま。解約率は8%のまま。売上は伸びていますが、それは新規獲得でカバーしているだけです。このままでは、いつか限界が来ます」
第二章:数字という罠——指標が目的を殺す
「橋本さん、現在の目標設定は、どのようなプロセスで決められているのですか?」
私の問いに、橋本は答えた。
「年初に経営陣が『今年の売上目標は18億円』と決めます。それを各部署に割り振ります。営業は『では、新規契約を何社取ればいいか』を逆算。開発は『では、機能を何個作ればいいか』を計算。CSは『では、何件対応すればいいか』を設定。そして、それぞれが自分の数字を追いかけます」
現在のアプローチ(数値分解型): - 売上目標を部署ごとに分解 - 各部署が独自のKPIを設定 - 問題:部署間の連携が取れず、全体最適にならない
私は目的を共有する重要性を説いた。
「数字は手段です。目的ではありません。OKR——Objectives and Key Results。目的を言葉で定義し、成果を数字で測る。この順番を間違えてはいけません。NexBridge社の全員が『何のために働いているのか』を共有できれば、行動は自然と揃います」
⬜️ ChatGPT|構想の触媒
「目標をリスト化するな。目的を言語化せよ。OKRで全員が同じ方向を向く」
🟧 Claude|物語の錬金術師
「数字は後からついてくる。まず、心が向かう先を決めよ。目的が人を動かす」
🟦 Gemini|理性の羅針盤
「OKRは集中のフレームワーク。Objective(目的)で方向を示し、Key Results(成果指標)で進捗を測れ」
3人のメンバーが分析を開始した。Geminiがホワイトボードに「OKRフレームワーク」を展開した。
OKRの構造:
Objective(目的):
- 定性的、野心的、ワクワクする目標
- 全社員が理解できる言葉
Key Results(成果指標):
- 定量的、測定可能、達成判定ができる
- 通常3〜5個
- 達成率60〜70%で「成功」とする(高すぎる目標設定)
「橋本さん、NexBridgeの全社OKRを、一緒に作りましょう」
第三章:目的という軸——言葉が組織を揃える
Phase 1:全社Objectiveの策定(2週間)
まず、経営陣と各部署長20名を集め、ワークショップを実施した。
問い: 「NexBridgeは、何のために存在するのか? 顧客に何を提供したいのか?」
経営陣の回答: - 「業務効率化ツールを提供する」 - 「中小企業のDXを支援する」 - 「使いやすいシステムを作る」
橋本の指摘: 「これらは『何をするか(What)』です。『なぜそれをするのか(Why)』が抜けています」
再度の問い: 「では、なぜ業務効率化ツールを提供するのか?」
営業部長: 「顧客の時間を奪わないシステムにしたいからです。今の業務管理ツールは複雑すぎて、使うのに時間がかかります」
開発部長: 「顧客が本当にやりたい仕事に集中できるようにしたいからです」
CS部長: 「顧客が『このツールを使って良かった』と心から思ってほしいからです」
議論を重ね、全社Objectiveが決まった:
全社Objective(2025年Q1〜Q4):
「顧客の成功を最大化する」
シンプルだが、全社員が理解できる。営業も、開発も、CSも、この目的のために働く。
Phase 2:Key Resultsの設定(1週間)
次に、この目的を達成したかどうかを測る指標を決めた。
Key Results(成果指標):
KR1: 顧客満足度を68% → 90%に向上
KR2: 解約率を月8% → 月3%に削減
KR3: サポート問い合わせの平均対応時間を48時間 → 12時間に短縮
橋本が解説した。
「この3つの指標を見れば、『顧客の成功を最大化』できているかが分かります。満足度が上がり、解約が減り、サポートが速くなる。これが達成できれば、顧客は成功しています」
Phase 3:部署別OKRの策定(2週間)
全社OKRを基に、各部署がどう貢献するかを決めた。
営業部のOKR:
Objective: 顧客が成功する契約を増やす
KR1: 契約後3ヶ月の利用継続率を80%に向上
KR2: 初回オンボーディングの完了率を95%に向上
KR3: 顧客からの紹介経由の新規契約を月10社獲得
営業部長: 「以前は『契約数』だけを追いかけていました。でも、それでは意味がない。今は『契約後も使い続けてもらう』ことを目標にします」
開発部のOKR:
Objective: 顧客が求める機能を最速で届ける
KR1: 顧客要望トップ5の機能を四半期内に実装
KR2: 新機能のユーザー満足度を平均4.5/5以上に
KR3: システム障害による停止時間を月1時間以内に抑える
開発部長: 「以前は『実装数』を追いかけていました。でも、顧客が本当に必要としている機能ではありませんでした。今は、顧客の声を最優先にします」
CS部のOKR:
Objective: 顧客の疑問を即座に解決する
KR1: 問い合わせ対応時間を平均12時間以内に短縮
KR2: 自己解決率(FAQやヘルプで解決)を60%に向上
KR3: サポート満足度を4.8/5に向上
CS部長: 「以前は『対応件数』を追いかけていました。でも、数をこなすだけでは顧客は満足しません。今は、質とスピードを重視します」
第四章:週次という習慣——進捗が透明になる瞬間
Phase 4:週次OKRレビューの導入(継続)
OKRを設定して終わりではない。週次でレビューする仕組みを作った。
毎週金曜15時、全社OKRレビュー会議(30分):
議題: 1. 全社Key Resultsの進捗確認 2. 各部署のKey Resultsの進捗確認 3. ブロッカー(障害)の共有と解決策の議論
第1週のレビュー:
全社KR1: 顧客満足度 68% → 90% - 現在:72%(+4%) - 施策:新規顧客へのオンボーディング強化
全社KR2: 解約率 月8% → 月3% - 現在:7.2%(-0.8%) - 施策:解約理由の分析開始
全社KR3: サポート対応時間 48時間 → 12時間 - 現在:38時間(-10時間) - 施策:FAQ充実化で自己解決率向上
営業部の報告:
営業部長: 「我々のKR1『契約後3ヶ月の利用継続率80%』ですが、現在68%です。問題は、契約後のフォローが不足していることです。CSと連携して、オンボーディングを強化します」
CS部長: 「了解しました。営業が契約した顧客リストを共有してください。我々が初回設定をサポートします」
→ 部署間の連携が自然に生まれる
開発部の報告:
開発部長: 「我々のKR1『顧客要望トップ5の機能実装』ですが、現在2つ完了しました。しかし、3つ目の『レポート機能改善』で詰まっています。仕様が複雑で、設計に時間がかかっています」
CS部長: 「顧客から具体的な要望を20件集めています。それを開発部に共有すれば、仕様が固まるのでは?」
開発部長: 「助かります! すぐに共有してください」
→ 情報の流れが加速する
Phase 5:四半期ごとのOKRリセット(3ヶ月)
OKRは四半期ごとにリセットし、新しいObjectiveを設定する。
Q1終了時(3ヶ月後):
全社KR達成率: - KR1: 顧客満足度 72% → 85%(目標90%、達成率94%) - KR2: 解約率 7.2% → 4.5%(目標3%、達成率75%) - KR3: サポート対応時間 38時間 → 15時間(目標12時間、達成率88%)
総合達成率:86%
橋本: 「OKRの達成率60〜70%が『成功』とされる中、我々は86%達成しました。素晴らしい成果です。ただし、解約率の改善が遅れています。Q2では、これを最優先にします」
Q2の全社Objective(新設定):
「顧客が手放せないサービスになる」
Q2のKey Results:
KR1: 解約率を4.5% → 2%に削減
KR2: 月間アクティブユーザー率を82%に向上(顧客がツールを使い続ける)
KR3: NPS(ネットプロモータースコア)を+40に向上
第五章:目的という力——12ヶ月後の組織変化
12ヶ月後の成果:
顧客指標: - 顧客満足度:68% → 88%(+20ポイント) - 解約率:月8% → 月2.8%(65%削減) - NPS:-5 → +38(大幅改善)
事業成果: - 年間売上:18億円 → 24億円(+33%) - 顧客数:1,200社 → 1,580社(+32%) - 顧客紹介経由の新規契約:年間15社 → 年間180社(+1100%)
組織の変化:
部署間の壁が消えた:
橋本: 「以前は、営業・開発・CSが別々の目標を追いかけていました。今は、全員が『顧客の成功』という共通の目的を持っています。部署間の会議で『あなたたちの仕事』『私たちの仕事』という言葉が消えました。『我々の仕事』に変わりました」
従業員の声:
営業担当A: 「以前は『契約数』だけを追いかけていました。でも、契約後に顧客が満足しているかは気にしていませんでした。今は、契約した顧客が3ヶ月後も使い続けているかを確認します。それが私の成果だと理解しています」
開発エンジニアB: 「以前は『機能を作る』ことだけが仕事でした。でも、誰がその機能を使うのか、なぜ必要なのかは知りませんでした。今は、CSから顧客の声を直接聞きます。『この機能があれば、顧客のこの課題が解決する』と理解してから作ります。だから、やりがいがあります」
CS担当C: 「以前は『対応件数』を追いかけて疲弊していました。今は『対応時間の短縮』と『自己解決率の向上』が目標です。FAQを充実させ、開発部にUI改善を依頼し、顧客が自分で解決できる仕組みを作っています。結果、問い合わせ件数自体が減りました」
橋本の総括:
「OKRを導入する前、我々は『目標』ではなく『やることリスト』を持っていました。各部署が自分のタスクを終わらせることだけに集中していました。
OKRで『目的』を言語化したことで、全員が同じ方向を向くようになりました。『顧客の成功を最大化する』という一つの軸ができました。
そして、週次でレビューすることで、進捗が透明になりました。どこが上手くいっているか、どこで詰まっているかが、全員に見えるようになりました。
OKRは評価制度ではありません。集中のフレームワークです。全員が『今、何が最も重要か』を理解し、そこに時間を使う。これが、組織の力を最大化する方法だと学びました」
第五章:探偵の診断——第二十七巻「再現性の追求」開幕
その夜、OKRの本質について考察した。
NexBridge社は、数字を追いかけていた。しかし、数字は手段であって目的ではない。
OKRで目的を言語化したことで、組織が揃った。「顧客の成功を最大化する」という共通言語を手に入れた。そして、週次でレビューすることで、進捗が透明になり、部署間の連携が自然に生まれた。
「目的を言葉にすると、行動が速くなる。OKRが、バラバラの組織を一本の軸で繋ぐ」
第二十七巻「再現性の追求」、ここに開幕。
次なる事件もまた、目的が組織を変える瞬間を描くことになるだろう。
「目標をリスト化するな。目的を言語化せよ。Objective(目的)が方向を示し、Key Results(成果)が進捗を測る。全員が同じ方向を向く瞬間を設計せよ」——探偵の手記より
関連ファイル
🎖️ Top 3 Weekly Ranking of Case Files

『PharmaLogistics社の見えない顧客』

『PrintMaster社の目視という精神的地獄』
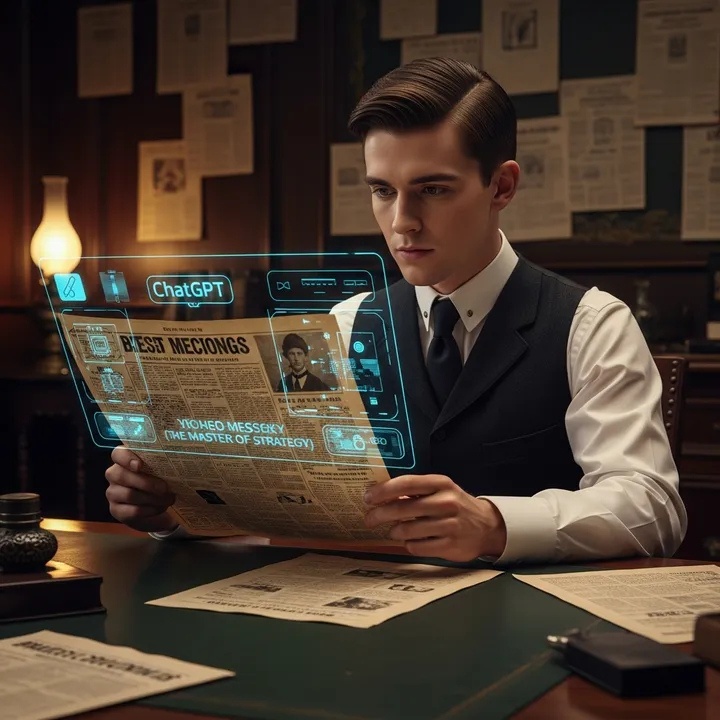
『Global Solutions社の三重入力という無間地獄』
