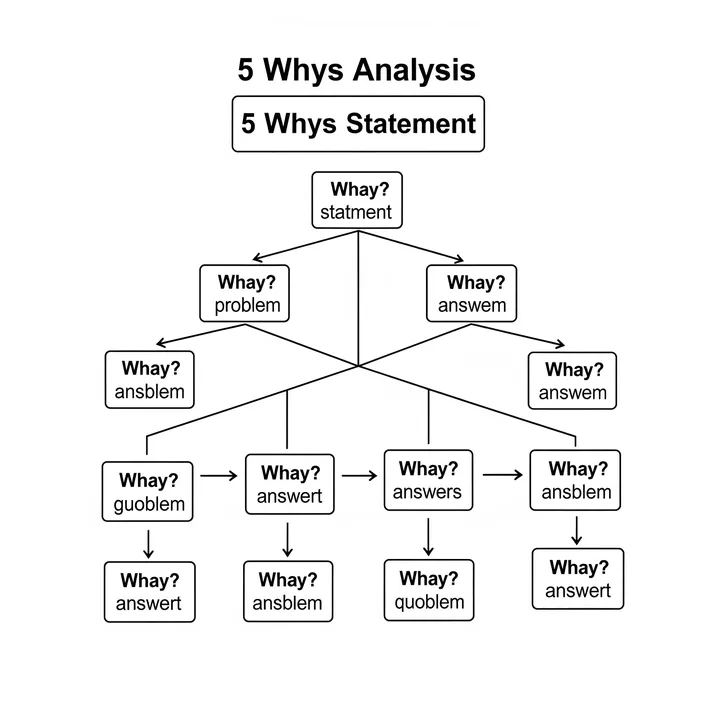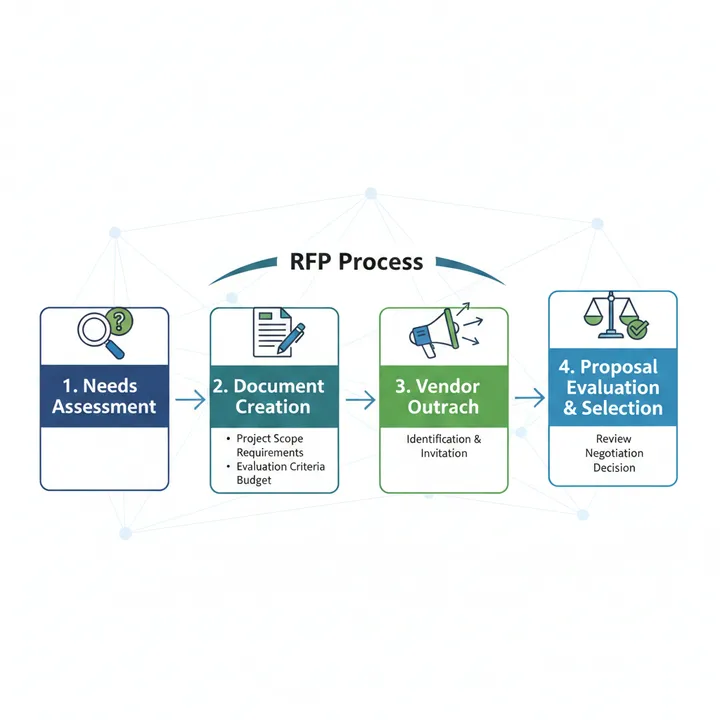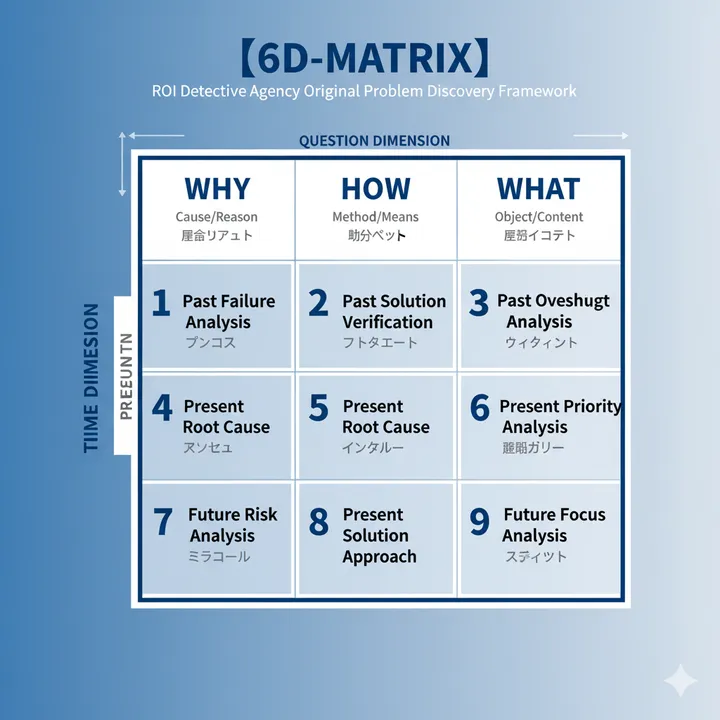ROI事件ファイル No.291|『SafeConstruct社の路面補修という迷宮』
📅 2025-11-01 23:00
🕒 読了時間: 14 分
🏷️ 5WHYS

第一章:繰り返される補修——終わらない悪循環
CircuitWorksのRCD事件が解決した翌週、今度は北関東から建設機械メーカーの奇妙な相談が届いた。第二十四巻「再現性の証明」の幕開けとなる第291話は、目に見える問題の奥に潜む真因を、5つの「なぜ」で掘り当てる物語である。
「探偵、我々の工場敷地内の路面補修費用が、毎年膨れ上がっています。損傷を見つけ次第すぐに直す。それなのに、翌月にはまた別の箇所が壊れる。いたちごっこです」
SafeConstruct社 の施設管理部長、栃木出身の田所健二は疲れ切った表情でベイカー街221Bを訪れた。彼の手には、5年分の補修記録と、それとは対照的に一向に減らない補修依頼書の束が握られていた。
「我々は栃木で建設機械を製造しています。ショベルカー、ブルドーザー。重量のある機械を毎日、工場内で移動させています。そのたびに、路面が傷む。補修する。また傷む。この繰り返しなのです」
SafeConstruct社の補修地獄: - 設立:1985年(建設機械メーカー) - 敷地面積:12万㎡ - 年間補修費用:2,800万円(5年前は980万円) - 補修頻度:月平均18箇所 - 補修方針:「損傷発見次第、即座に対応」 - 効果:一向に減らない補修箇所
田所の声には深い諦めがあった。
「我々は真面目に対応しています。ひび割れを見つければすぐにアスファルトで埋める。陥没があれば即座に整地する。それでも、補修費用は年々増える一方です。もう、どうすればいいのか分かりません」
第二章:問いの連鎖——5つの「なぜ」が導く真実
「田所さん、補修が必要になる理由について、どのような分析をされてきましたか?」
私の問いに、田所は答えた。
「理由は明白です。重機が通るから路面が傷む。それだけです。建設機械を扱っている以上、これは避けられないコストだと諦めていました」
現在の理解(表層的): - 原因:重機の走行 - 対策:損傷箇所の迅速な補修 - 結論:「仕方がない」
私は問題の本質を掘り下げる重要性を説いた。
「『なぜ?』を繰り返すことで、表面の症状から真の原因へと辿り着く。5WHYS——5回の『なぜ』が、見えない根源を照らし出すのです」
⬜️ ChatGPT|構想の触媒
「問題の表面を撫でるな。5つの『なぜ』で、根っこまで掘れ」
🟧 Claude|物語の錬金術師
「症状を治すのは対症療法。原因を絶つのが根治療法。5WHYSは、根源への階段だ」
🟦 Gemini|理性の羅針盤
「問いは剣。表層を切り裂き、核心に至る。5回斬れ」
3人のメンバーが分析を開始した。Geminiがホワイトボードに「5WHYS分析」のフレームワークを展開した。
5WHYSの原則: - 1回目の「なぜ」:表面的な原因 - 2回目の「なぜ」:中間的な原因 - 3-4回目の「なぜ」:構造的な原因 - 5回目の「なぜ」:根本原因
「田所さん、SafeConstructの補修問題を、5つの『なぜ』で掘り下げましょう」
第三章:階段を降りる——問いが明かす隠された真実
第1の「なぜ」:なぜ補修頻度が多いのか?
田所の答えは即座だった。
「路面の劣化が早いからです。通常なら10年持つはずのアスファルトが、2-3年で傷んでしまいます」
発見: - 問題:劣化速度が異常に速い - 通常の3-5倍のスピードで損傷
第2の「なぜ」:なぜ劣化が早いのか?
「重機の走行負荷が高いからです。50トン級のブルドーザーが、毎日何十台も通ります」
しかし、ここで私は尋ねた。
「他の建機メーカーも同じ条件のはずです。なぜSafeConstructだけが、これほど補修が多いのでしょう?」
田所は言葉に詰まった。
現場を実際に観察することにした。
現場観察(3日間): - 重機の移動ルートを記録 - 損傷箇所の分布を地図化 - 発見:損傷は「特定の箇所」に集中していた
損傷集中エリア:
- エリアA(組立工場前):月8回の補修
- エリアB(塗装工場への導線):月6回の補修
- エリアC(出荷ゲート前):月4回の補修
- その他のエリア:月平均0.3回
田所は驚愕した。
「つまり、路面全体が劣化しているのではなく、特定の場所だけが集中的に傷んでいるのですね」
第2の答え: - 原因:特定ルートへの負荷集中 - 重機走行そのものより「走行の偏り」が問題
第3の「なぜ」:なぜ特定ルートに負荷が集中するのか?
重機の移動記録を詳細に分析した。
発見された移動パターン: - 組立工場→塗装工場:1日80往復 - 塗装工場→検査場:1日65往復 - 検査場→出荷ゲート:1日70往復
「なぜ、こんなに往復が多いのでしょう?」
現場のオペレーターに聞き取りをした。
オペレーターの証言: 「組立が終わったら塗装に運ぶ。でも塗装工場は敷地の反対側だから、毎回長距離を移動するんです。検査場もまた別の場所。効率が悪いのは分かっていますが、工場の配置がそうなっているので仕方ありません」
第3の答え: - 原因:工場配置(レイアウト)の非効率性 - 必要以上の長距離移動が発生
第4の「なぜ」:なぜ工場配置が非効率なのか?
設計図面を取り寄せた。
工場は1985年の創業時に設計され、その後の増築で以下のような配置になっていた:
工場配置の変遷: - 1985年:組立工場のみ(敷地3万㎡) - 1998年:塗装工場を増設(敷地北端に) - 2007年:検査場を増設(敷地南端に) - 2015年:出荷ゲートを増設(敷地東端に)
田所は頭を抱えた。
「増設のたびに、空いている土地に建ててきました。結果として、工程の順番と建物の配置が、バラバラになってしまったのです」
第4の答え: - 原因:増築を繰り返した結果の非最適配置 - 設計時に「動線」を考慮していなかった
第5の「なぜ」:なぜ設計時に動線を考慮しなかったのか?
これが最後の問いだった。
過去の設計資料を調べると、驚くべき事実が判明した。
設計時の判断基準: - 土地取得コスト:最優先 - 建設費用:2番目 - 動線効率:考慮されていない
設計担当者(当時)の記録には、こう書かれていた:
「工場の配置は、土地の取得しやすさで決定した。作業効率は後から調整可能と判断」
しかし、その「後からの調整」は一度も行われなかった。
第5の答え(根本原因): - 原因:設計時に現場の運用データを活用しなかった - 「動線」という無形の価値が、設計の判断基準に含まれていなかった
第四章:根源への処方箋——5WHYSが描く解決の道筋
ホームズが分析をまとめた。
「田所さん、問題の本質は『路面が弱い』ことではありません。『動線設計が誤っている』ことです。5WHYSによって、我々は表層の症状から、20年前の設計判断という根源に辿り着きました」
5WHYSの結論: 1. 補修が多い → 劣化が早い 2. 劣化が早い → 負荷が集中 3. 負荷が集中 → 動線が非効率 4. 動線が非効率 → 設計が悪い 5. 設計が悪い → 現場データ未活用
根本対策の立案:
短期対策(6ヶ月、投資580万円): - 損傷集中エリアの路面強化 - 高耐久アスファルトへの変更 - 効果:補修頻度50%削減(対症療法)
中期対策(18ヶ月、投資2,400万円): - 仮設の連絡通路を新設 - 塗装工場と検査場を最短距離で結ぶ - 効果:移動距離30%削減、補修頻度70%削減
長期対策(5年計画、投資2.8億円): - 工場全体のレイアウト再設計 - 組立→塗装→検査→出荷の一直線配置 - 効果:移動距離60%削減、補修費用90%削減
12ヶ月後の成果:
短期と中期対策を実施した結果:
補修費用: - 年間2,800万円 → 年間720万円(74%削減)
補修頻度: - 月平均18箇所 → 月平均5箇所(72%削減)
移動効率: - 重機の総移動距離:35%削減 - 作業時間:1日あたり2.5時間削減 - 燃料費:年間420万円削減
組織の変化: 「補修する組織」から「設計する組織」へ
第五章:探偵の診断——第二十四巻「再現性の証明」開幕
その夜、問いの力について考察した。
5WHYSの真価は、諦めない姿勢にある。
最初の答え「重機が通るから」で思考を止めれば、永遠に対症療法を繰り返すことになる。
しかし、「なぜ?」を5回繰り返すことで、20年前の設計判断という根源に辿り着いた。
「問題の9割は、表面ではなく深層にある。問い続ける者だけが、真の解決に至る」
第二十四巻「再現性の証明」、ここに開幕。
次なる事件もまた、問いの連鎖が企業の未来を切り開く瞬間を描くことになるだろう。
「『なぜ?』を5回問え。表層を超え、核心に至るまで。真の原因は、常に深淵に潜んでいる」——探偵の手記より
関連ファイル
あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!
月額980円で200万冊以上の本が読み放題。
ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!
※対象となる方のみ無料で体験できます