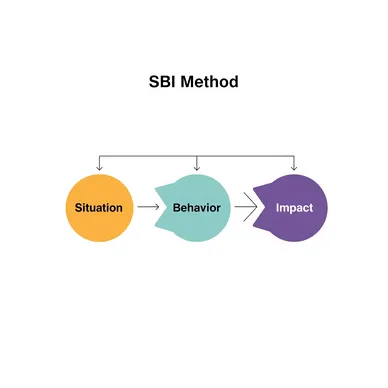ROI事件ファイル No.289|『ElectroMartの承認迷路』
📅 2025-10-31 23:00
🕒 読了時間: 21 分
🏷️ SBI

第一章:回らないワークフロー——複雑化した承認プロセスの罠
Memoria社のMECE整理事件が解決した翌週、今度は関東から家電量販チェーンのグループウェア問題に関する相談が届いた。第二十三巻「再現性の追求・続編」の第289話は、複雑に絡み合った問題の因果を解きほぐし、本質を見抜く物語である。
「探偵、我々のワークフローシステムが現場で使われていません。5年前、業務効率化のためにオープンソースのグループウェアを導入しました。しかし今、そのシステムが業務を妨げています。承認が遅れ、現場は混乱し、結局、紙とメールに戻っています」
ElectroMart の業務改革室長、東京出身の佐藤健一は困惑を隠せずにベイカー街221Bを訪れた。彼の手には、複雑な承認フローの設計図と、それとは対照的に「システム利用率12%」と記された利用状況レポートが握られていた。
「我々は関東・東海地区で家電量販店を42店舗展開しています。店舗からの稟議、経費申請、休暇申請など、全てをワークフローシステムで管理するはずでした。しかし、誰も使いません」
ElectroMart のワークフロー崩壊: - 設立:1995年(家電量販チェーン) - 年間売上:680億円 - 店舗数:42店舗 - 従業員数:1,850名 - グループウェア導入:2020年(オープンソース) - 導入コスト:初期1,200万円 + 年間保守480万円 - システム利用率:12%(目標80%) - 紙ベース申請:月平均1,200件(減らない) - 承認遅延:平均8.5日(目標2日)
佐藤の表情には深い焦燥があった。
「問題は、現場が『使いにくい』と言うことです。システム部門は『設計通りに作った』と言い、現場は『複雑すぎて分からない』と言います。誰が悪いのか、何が問題なのか、全く見えません」
現場の声(店舗スタッフ): - 「申請の種類が多すぎて、どれを選べばいいか分からない」(68%) - 「承認者を自分で選ぶが、誰に送ればいいか分からない」(72%) - 「入力項目が多く、時間がかかる」(58%) - 「システムが遅くて、イライラする」(45%) - 「結局、店長に直接聞いた方が早い」(82%)
管理部門の声: - 「現場が使ってくれない。何度研修しても無駄」 - 「せっかく作ったのに、投資が無駄になっている」 - 「紙とメールが残るので、二重管理で手間が増えた」
システム部門の声: - 「要望通りに作った。使わないのは現場の問題」 - 「これ以上シンプルにできない。承認プロセスは複雑だから」 - 「カスタマイズにはさらに予算が必要」
「我々は原因が分かりません。システムが悪いのか、現場が悪いのか、運用が悪いのか。全ての可能性が指摘され、結局、何も改善できていません」
第二章:因果の連鎖——状況・行動・影響を解きほぐす
「佐藤さん、現在の問題分析は、どのように行われているのでしょうか?」
私の問いに、佐藤は答えた。
「基本的には『誰が悪いか』を探しています。システム部門は現場を責め、現場はシステムを責め、管理部門は両方を責めます。会議では、犯人探しと責任のなすり合いです」
現在の問題分析(犯人探し型): - システム部門:「現場が使い方を覚えない」 - 現場:「システムが複雑すぎる」 - 管理部門:「誰も責任を取らない」 - 結果:対立が深まり、改善が進まない
私は因果関係の構造化の重要性を説いた。
「問題は『誰か』ではなく『なぜ』です。SBI——Situation(状況)、Behavior(行動)、Impact(影響)。この3つの因果を解きほぐせば、真の問題が見えてくるのです」
⬜️ ChatGPT|構想の触媒
「犯人を探すな。因果を探せ。状況が行動を生み、行動が影響を生む」
🟧 Claude|物語の錬金術師
「問題は人ではなく、構造にある。SBIは構造を可視化する鍵だ」
🟦 Gemini|理性の羅針盤
「SBI分析は因果の地図。状況→行動→影響の連鎖を追え」
3人のメンバーが分析を開始した。Geminiがホワイトボードに「ワークフロー特化型SBI分析」のフレームワークを展開した。
SBIフレームワークの3要素: 1. Situation(状況) - どんな状況・環境にあるか 2. Behavior(行動) - その状況で何をするか 3. Impact(影響) - その行動が何を引き起こすか
「佐藤さん、ElectroMartのワークフロー問題を、SBIで因数分解しましょう」
第三章:因果の可視化——見えなかった連鎖
Phase 1:現場観察(1週間)
会議室での議論ではなく、実際の業務現場を観察した。
観察対象:店舗スタッフ3名(1日密着)
観察事例1:店舗スタッフA(28歳、勤続3年)
Situation(状況): - 勤務中、急に体調不良 - 休暇を取りたい - 手元にあるのはスマホのみ(PC未起動)
Behavior(行動): 1. ワークフローシステムにアクセス試みる 2. スマホでは画面が見づらく、入力しづらい 3. 「どの申請フォームか分からない」と混乱 4. 諦めて、店長に電話で直接連絡 5. 後日、紙の休暇届を提出
Impact(影響): - システムは使われない - 紙とメールによる二重管理 - システム利用率が上がらない
観察事例2:店長B(45歳、店長歴8年)
Situation(状況): - 承認待ちの通知が20件溜まっている - 店舗業務で接客・在庫管理に追われている - PCを開く時間は1日1-2回のみ
Behavior(行動): 1. 承認画面を開く 2. 各申請の内容を確認(1件あたり3-5分) 3. 「これは誰に次に回せばいいか?」と悩む 4. 承認ルールを確認するが、複雑で理解できず 5. 結局、部下に直接確認 6. 承認処理に1時間かかる 7. 疲弊し、残りは「後で」と先送り
Impact(影響): - 承認が遅延(平均8.5日) - 部下は「承認待ち」でイライラ - 店長も「承認作業」でイライラ
Phase 2:SBI構造の可視化(3日)
観察から、問題の因果連鎖を図式化した。
SBI連鎖図:
【Situation 1】現場スタッフの状況
└→ スマホ中心の業務スタイル
└→ PC利用は限定的(1日1-2回)
└→ 急な申請が必要な場面が多い
【Behavior 1】現場スタッフの行動
└→ システムにアクセス試みる
└→ スマホでは使いにくい(画面・操作性)
└→ 諦めて、電話・紙で対応
【Impact 1】システム回避
└→ 利用率12%
└→ 紙・メールが残る
└→ 二重管理の手間
【Situation 2】承認者(店長)の状況
└→ 承認待ち20件が常時ある
└→ 店舗業務で時間がない
└→ 承認ルールが複雑
【Behavior 2】承認者の行動
└→ 承認を後回しにする
└→ 分からない時は部下に直接確認
└→ システムより直接コミュニケーション
【Impact 2】承認遅延
└→ 平均8.5日待ち
└→ 現場の不満蓄積
└→ 「システムは使えない」という認識定着
【悪循環】
Impact 1 + Impact 2 → Situation 1,2 の悪化
佐藤は愕然とした。
「誰も悪くないのですね。状況が行動を生み、行動が影響を生み、その影響が状況を悪化させる。負のループです」
Phase 3:根本原因の特定
SBI分析から、真の問題が見えた。
根本原因1:Situationの設計ミス - システムが「PCで使うもの」として設計されている - しかし現場の状況は「スマホ中心」 - 状況と設計のミスマッチ
根本原因2:承認フローの複雑性 - 承認ルールが10パターン以上 - 承認者が「自分で次の承認者を選ぶ」仕様 - 現場の認知負荷が高すぎる
根本原因3:影響のフィードバックループ - 使いにくい → 使わない → 紙が残る → システムが使われない - 負のスパイラルが固定化
第四章:因果の逆転——状況を変え、行動を変え、影響を変える
Phase 4:SBIベースの改善設計(2週間)
因果を理解したので、その連鎖を逆転させる設計をした。
改善戦略:状況を変えれば、行動が変わる
改善1:Situationの再設計(スマホファースト)
新しい状況: - スマホアプリで全ての申請が完結 - 音声入力対応(タイピング不要) - 写真添付で証憑も簡単
期待される行動変化: - スマホで即座に申請(PC不要) - 外出先でも申請可能 - 入力の手間削減
期待される影響: - 利用率向上 - 紙・メール削減
改善2:承認フローの自動化
新しい状況: - 申請の種類で承認ルートが自動決定 - 承認者は「承認」「却下」のみ(次の承認者選択不要) - 承認期限(48時間)を過ぎると自動エスカレーション
期待される行動変化: - 店長は迷わず承認できる - 承認作業が1件1分以内 - タイムリーな承認
期待される影響: - 承認期間短縮 - 店長の負担軽減
改善3:申請フォームの簡素化
新しい状況: - 申請タイプを3種類に集約(休暇・経費・稟議) - 入力項目を50%削減(必須のみ) - 過去の申請をテンプレート化(ワンクリック再利用)
期待される行動変化: - 申請が30秒で完了 - 入力ミス削減
期待される影響: - 申請のハードル低下 - 利用率向上
Phase 5:段階的実装(3ヶ月)
Step 1:スマホアプリ開発(6週間) - ネイティブアプリ開発(iOS/Android) - 音声入力、写真添付、プッシュ通知 - 予算:480万円
Step 2:承認フロー再設計(4週間) - 承認ルートの自動化 - 期限管理とエスカレーション - 予算:180万円
Step 3:パイロット運用(4週間) - 5店舗で先行導入 - フィードバック収集と改善 - 全店展開準備
3ヶ月後の成果:
Situationの変化: - スマホで全て完結可能に - 現場の状況に合致したシステム
Behaviorの変化: - システム利用率:12% → 68% - 申請時間:平均8分 → 平均45秒 - 承認時間:平均8.5日 → 平均18時間
Impactの変化: - 紙ベース申請:月1,200件 → 月120件(90%削減) - 承認遅延クレーム:月45件 → 月2件 - 管理部門の処理時間:月240時間 → 月30時間
Phase 6:正のスパイラルの創出(6ヶ月)
負のループが正のループに変わった。
正のスパイラル:
【新Situation】スマホで簡単に使える
↓
【新Behavior】みんなが使う
↓
【新Impact】業務が効率化される
↓
【フィードバック】さらに使いたくなる
↓
【新Situation】「これは便利」という認識が定着
12ヶ月後の総合成果:
システム利用の定着: - 利用率:12% → 92% - 新入社員:システム研修30分で習得(以前は半日) - スタッフ満足度:2.3 → 4.6
業務効率の飛躍: - 申請〜承認完了:平均8.5日 → 平均12時間 - 管理部門の工数:年間2,880時間 → 年間360時間(87%削減) - 紙・印刷コスト:年間280万円 → 年間20万円
意思決定の高速化: - 経営判断に必要な稟議:平均2週間 → 平均2日 - ビジネス機会損失の削減 - 現場の提案が通りやすくなった
組織の変化: - 「システムは敵」→「システムは味方」 - IT投資への理解が深まった - 他部門からも「同じように改善してほしい」という要望
現場の声:
店舗スタッフA(28歳): 「以前は申請が面倒で、ギリギリまで我慢していました。今はスマホで30秒。気軽に申請できるので、働きやすくなりました」
店長B(45歳): 「承認作業が苦痛でした。今は通勤中の電車でサッと承認できます。部下からの『まだですか?』というプレッシャーもなくなりました」
第五章:探偵のSBI診断——因果を解けば、問題は消える
ホームズが総合分析をまとめた。
「佐藤さん、SBIの本質は『構造理解』です。問題は人ではなく、状況にあります。状況が行動を生み、行動が影響を生む。この因果を理解すれば、状況を変えることで、全てが変わるのです」
24ヶ月後の最終報告:
ElectroMartは家電量販業界で「最も業務効率の高い企業」として評価された。
最終的な成果: - 年間売上:680億円 → 748億円(+10%) - 業務効率化による人件費削減:年間1.2億円 - 意思決定スピード:業界トップ - 従業員満足度:業界1位
佐藤からの手紙には深い感謝が記されていた:
「SBI分析によって、我々は『犯人探しの組織』から『構造改善の組織』へと変わりました。最も重要だったのは、『誰が悪い』ではなく『何が問題か』を問うようになったことでした。状況が行動を生むなら、状況を変えれば行動が変わります。今では新しい問題に直面した時、必ずSBIで分析します。問題は人ではなく、構造にあるのだと理解しました」
探偵の視点——因果を解く者が、未来を変える
その夜、問題解決の本質について考察した。
SBIの真価は、非難からの解放にある。問題が起きると、人は誰かを責める。しかし、多くの場合、誰も悪くない。状況が行動を生み、行動が影響を生んでいるだけだ。
因果を理解すれば、非難は消える。そして、状況を変えることに集中できる。状況が変われば、行動が変わる。行動が変われば、影響が変わる。
「問題の犯人を探す者は、永遠に問題と戦う。因果を解く者だけが、問題を消せる」
次なる事件もまた、SBI思考が企業の未来を切り開く瞬間を描くことになるだろう。
「人を責めるな。状況を変えよ。状況が行動を生み、行動が未来を創る」――探偵の手記より
事件ファイル
あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!
月額980円で200万冊以上の本が読み放題。
ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!
※対象となる方のみ無料で体験できます